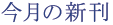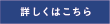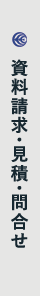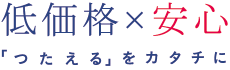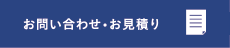「常用漢字」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「政府で定められた漢字?」「これ以外の漢字は使ってはいけない?」
など、さまざまなイメージがあるかもしれません。
この記事では「常用漢字」について解説します。
目次
漢字はいくつある?
ひらがなやアルファベットなど、大抵の言語で使われる文字の数は数十字程度です。
しかし漢字は、膨大な数があります。いったいどのくらいの数があるのでしょうか?
たとえば日本のコンピューターの文字入力でよく使われる「Shift_JIS」には、一万字を超える漢字が登録されています。
また、漢字が生まれた中国で編纂されている漢字辞書には、5万~10万字超の漢字が収録されています。
長い歴史を誇り、広大な地域で使われてきた漢字の正確な総数はわかりません。
漢字を利用する目安
膨大な種類がある漢字ですが、これらすべての漢字を日常的に使用することは現実的ではありません。
公文書や報道などで漢字を無秩序に使用すると、同じ単語でも別の漢字が使われていたり、特定の人にしかわからない文章になってしまう可能性があります。
そのような混乱を避けるために文化庁によって定められているのが「常用漢字」です。
常用漢字とは、「法令,公⽤⽂書,新聞,雑誌,放送など,⼀般の社会⽣活において,現代の国語を書き表す場合の漢字使⽤の⽬安を⽰すものである。」(常用漢字表)とされています。
制定以来、アップデートが続けられており、たとえば2010年に改定された常用漢字には、新しく 熊 塾 携 謎 鬱 など196字が追加されるなど変更が加えられました。
現行の常用漢字表には、2136字が収められており、下記文化庁ウェブサイトをはじめ、さまざまな場所から参照できます。
●常用漢字表(文化庁ウェブサイト)
https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/kanji/
どこで使われる?
主に常用漢字に則って漢字が利用されるのは、公文書、法令文書、新聞・雑誌などの出版物、教科書、テレビ・ラジオなどの放送媒体、ビジネス文書などです。
概ね、難しい漢字、マイナーな漢字を利用することなく、混乱がないように多くの人に情報を届ける必要がある場合に利用されるものといえます。

ただし、これはあくまでも目安・基準であり、創作・研究などの自由な表現を妨げるものではありません。
常用漢字でない専門用語や固有名詞はたくさんありますし、文学作品などでは常用漢字にとらわれずさまざまな漢字を利用しているものがほとんどです。
あくまで、作成する原稿の目的や読者に沿うための目安として「常用漢字表」を活用してみましょう。
まとめ
●「常用漢字」は、膨大な数がある漢字のうち、日常で利用する漢字の目安
●主に公文書、法令文書、新聞・雑誌などの出版物、教科書、テレビ・ラジオなどで利用される
●あくまで目安なので、常用外の漢字の使用も自由